E-mail newsletterメルマガ配信
第166号 剣道愛好家必見!竹刀・剣道具の安全基準について(その1)
剣道は日本古来の武道として多くの人に親しまれていますが、過去には竹刀の先端が面の物見部に貫入したり、打ち合いの際に破損し、その破片が面の間を抜けて目の下に突き刺さるといった事故が発生していました。こうした危険を防ぐため、1998年に竹刀および剣道具のSG基準がそれぞれ制定され、安全性が確保されるようになりました。
竹刀は、剣先が折れたり破片が飛び散ったりすると、目や顔に重大な怪我をする恐れがあります。そのため、SG基準では、竹刀の外表面にささくれがないこと、剣先の直径が一定以上であることを求めています。竹刀の長さが1,140㎜以下のものと1,140㎜を超えるものでは、それぞれ最小直径が規定されており、剣先折れたり割れたりしにくい十分な強度が確保されるようになっています。
また、竹刀の組み立てが適切に行われていることも重要です。ため傷(※1)や割れがないことが確認される必要があり、剣先には一定の圧力が加えられた際にも破損しない強度が求められます。さらに、竹のピース(ちくとう)は1,500N (※2)の剪断荷重に耐えられるよう設計されており、これによって竹刀の破損リスクを減らし、使用者の安全を確保しています。
※1:ため傷とは、竹刀の表面や内部にできる圧力による傷を指します。「ため」とは、竹の繊維に沿って蓄積された力によって生じる小さなひび割れや亀裂のことで、見た目には分かりにくいのが特徴です。
※2:約150kg相当の力
さらに、SG基準では竹刀に関する適切な表示や取扱説明も義務付けています。たとえば、竹刀の長さや使用対象(男性用・女性用)の明記、取扱説明書への点検方法や修理方法、使用上の注意点の記載などです。これにより、使用者が安全に竹刀を扱えるよう配慮されています。
しかし、SG基準を満たした竹刀であっても、日々の点検とメンテナンスを怠ると安全性は確保できません。稽古の前後には、竹刀にささくれやヒビがないかを確認し、先革や弦(つる)が適切に固定されているか、剣先の形状が崩れていないかをチェックする習慣をつけることが大切です。こうした日々の点検が、剣道を安全に楽しむための第一歩となります。
次回のメルマガでは、剣道具の安全基準について詳しくお伝えする予定です。お楽しみに!
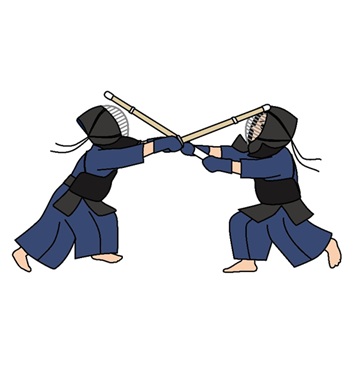
2024年度





